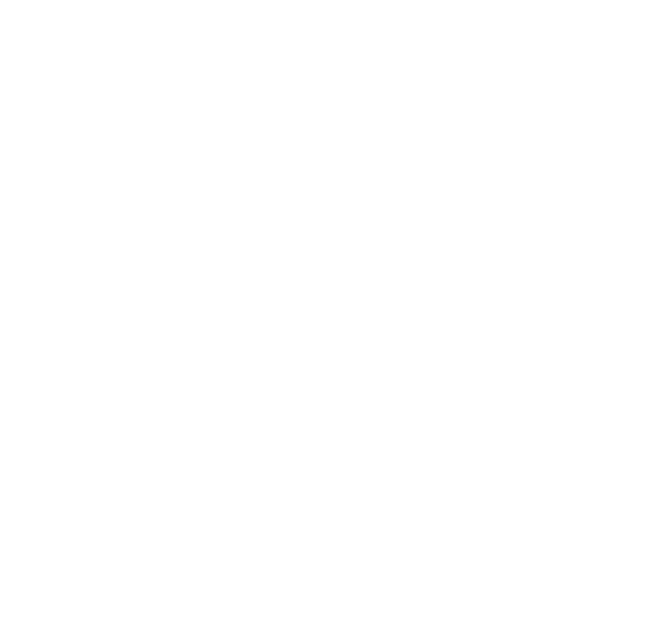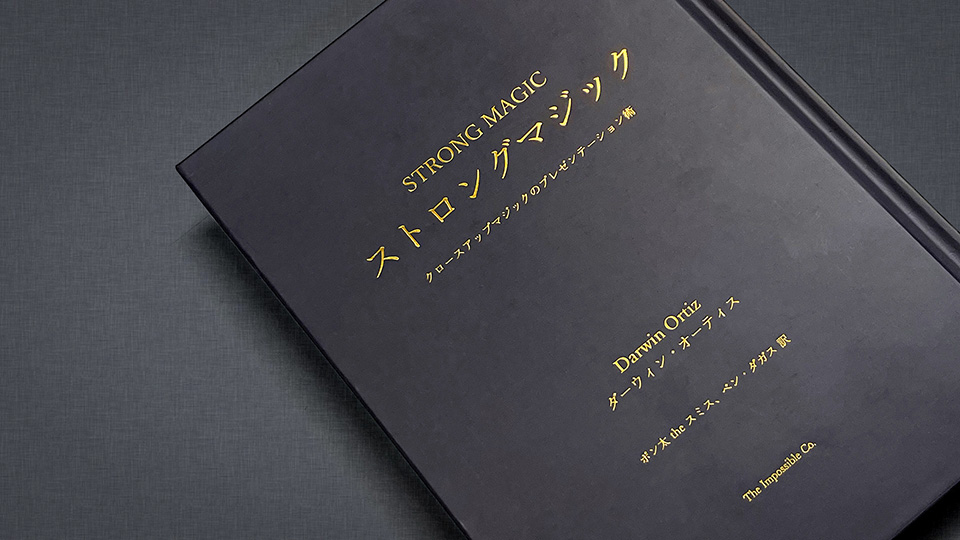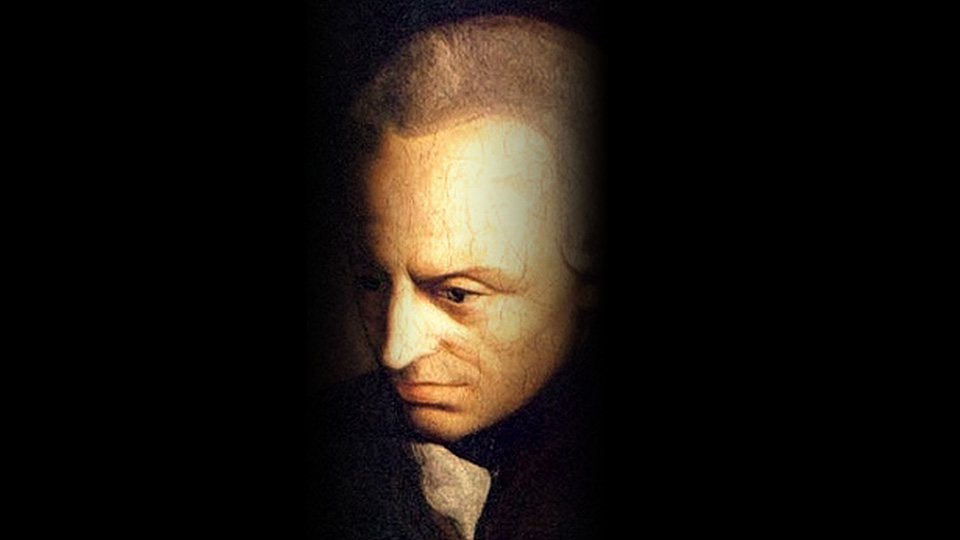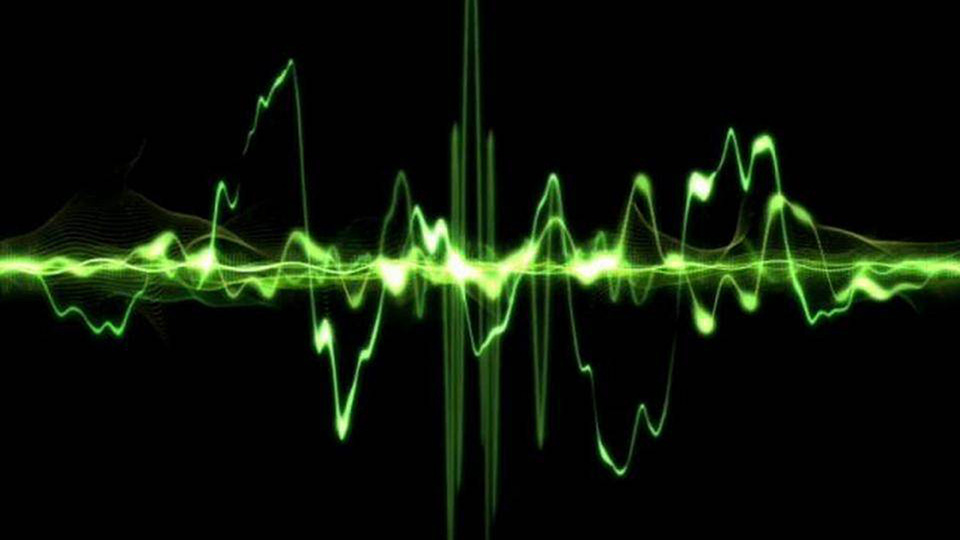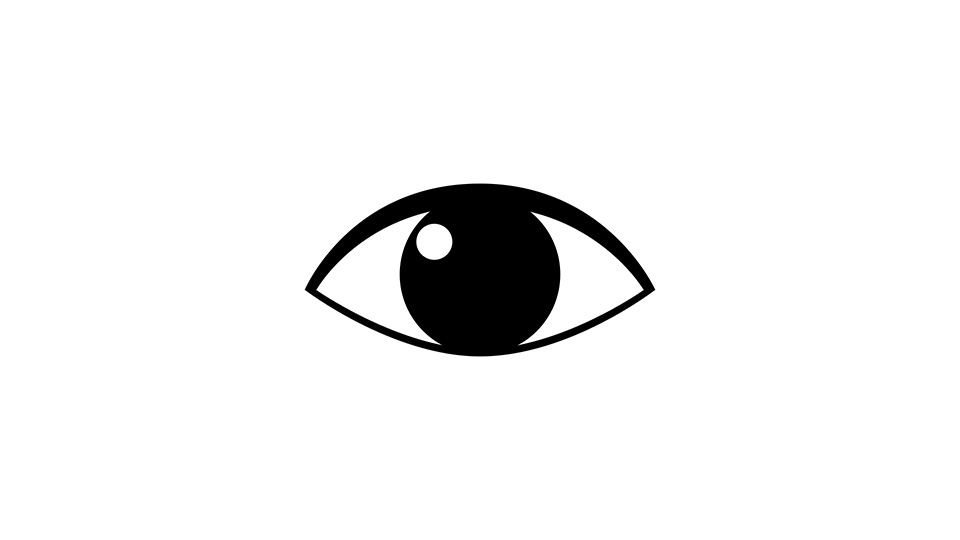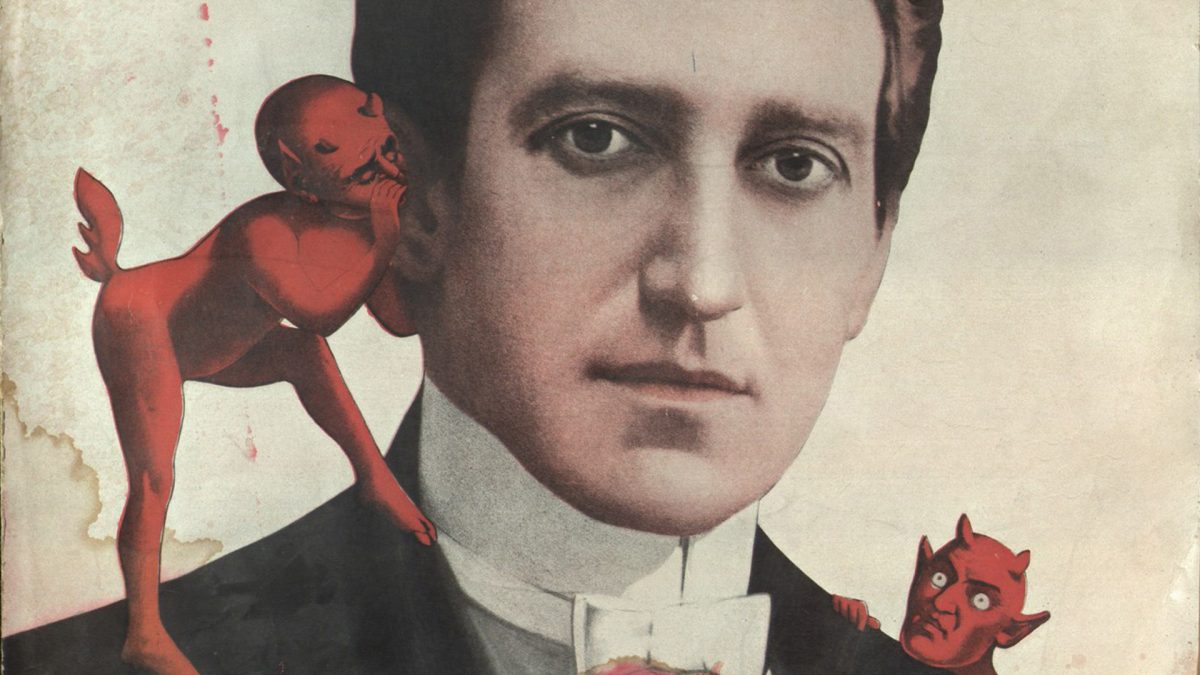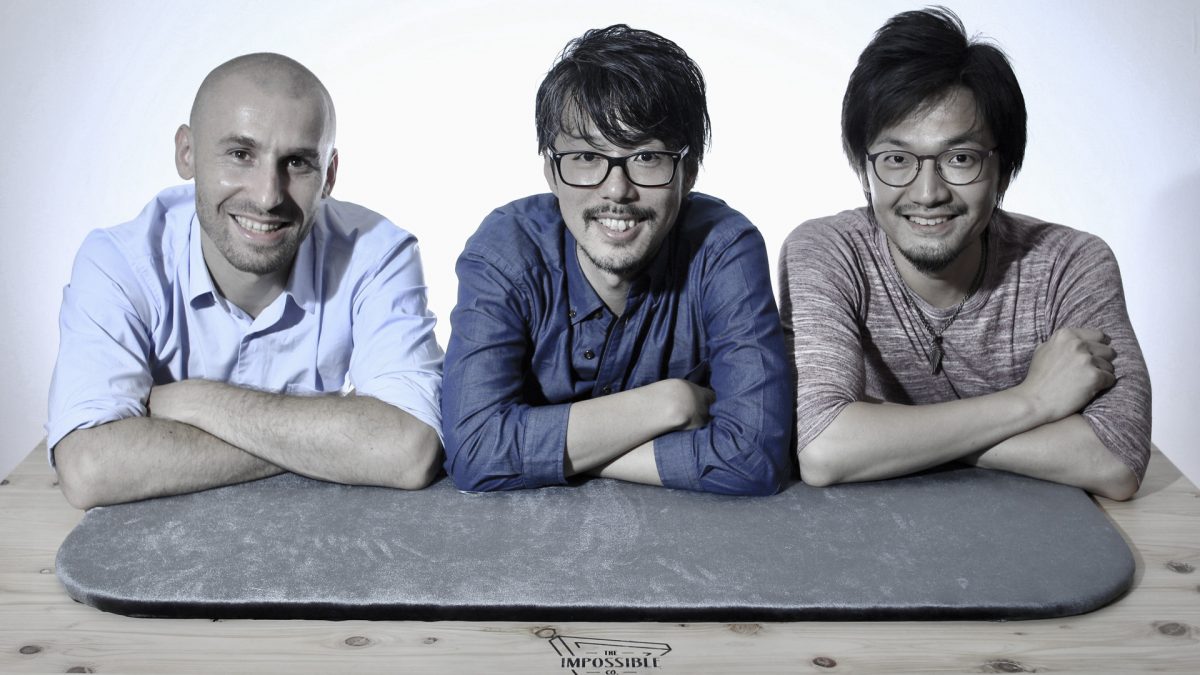マジックの世界には大小さまざまなコンテストがあります。私もいろんなコンテストにいろんな形でかかわってきました。
近年、マジック界でのコンテストの意義がますます高まってきているように感じます。そこで、あらためて「マジックコンテスとはどういうものなのか」をあれこれ書きました。
マジックコンテストの意義
コンテストの意義とはなんでしょうか。それはコンテストによっても異なりますが、だいたいは要約すれば技術の向上および文化の発展といったところになるでしょう。お笑いはM-1をはじめとするコンテストが盛り上がることで、芸人の技術が切磋琢磨され、それがエンタメの強度となり、お笑い文化の繁栄につながっています。繁栄しすぎているきらいはありますが。
ともあれ、娯楽が多様化し、娯楽性に対する基準や要求が高まっていくなかで、止まったままのものは落ちていくしかありません。「その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない」のです(『鏡の国のアリス』)。
「真剣にやれよ、仕事じゃねえんだぞ」(タモリ)ではありませんが、ビジネスではないから全力投入できるということがあります。ビジネスでは、得られるメリットから投下するコスト(時間や努力も含まれます)を決めるので、マジックのような市場規模では熱量不足で大したことができません。ニッチなジャンルは商業主義ではなかなか発展しにくいわけです。
良いマジシャンは非商業主義的なエンジンも積んでいます。そもそも、商業と割り切るならなぜマジックなのか。もっと効率のいい商売をしたほうがいいでしょう。結局、我々はマジックが好きでやっている(少なくとも好きではじめた)のであり、マジックに精神的価値を感じており、その価値を追求する気持ちがある(あった)はずです。
商業性を否定するわけではありません。それはプロ には必要条件とも言えるでしょう。でもそれは十分条件ではありません。商業性やマーケットインに傾きすぎると、逆説的ですが商業は先細りになります。「市場や顧客のニーズを意識しすぎて日本企業は凋落した」とスティーブ・ジョブズは言いました。マジックはこのところ、資源と需要を消費するばかりのサイクルで弱体傾向にないでしょうか。
マジックの発展には、商業主義以外の価値基準も重要になります。それを育むもののひとつがコンテストです。コンテストで、マジックやマジシャンの卓越性、創造性、芸術性を認め、励ますことで、その価値観のカルチャーが広がり成長します。文化的価値が賞を介して商業的価値になることもあるでしょう。それは基本的には文化と商業の双方に強度をもたらすものになります。そのような活性化を通じて、マジックに健全な発展を促すのが、コンテストの望ましいあり方であり、その存在意義だと私は思います。
参加意義
では、コンテストの出場する意義はなんでしょうか。なぜコンテストに出るのか。これもまたコンテスタントによるわけですが、自分の実力を試したい、示したいというのがとりあえずの動機なるかと思います。そこでの経験と成長も意義として大きいでしょう。もう少し進んだフェイズでは、創作や研鑽のモチベーションにしたい、ステップアップにつなげたいといった視点も出てきます。
出場するメリットはたくさんあります。まず、挑戦自体が自信になるでしょう。人生の後悔ランキングのトップは挑戦しなかったことです。挑戦できるという資質は大きいのです。また、マジックコンテストへの出場は、マジックへの情熱の証明になります。情熱で開かれる扉は少なくありません。そして、幸運にも好成績なら、当然、それ自体が喜ばしいことですし、そこから広がるチャンスも増えるでしょう。
そして、そもそも、コンテストはコンテスタントがいないと成立しません。つまり、コンテスタントはマジックの文化を支える重要なプレイヤーなわけです。
したがって、コンテストは参加することに大きな意義があると言えるわけですが、しかしやはり出るからには勝ちたいというのもあるでしょう。
コンテストで勝つには
必勝法はありません。個別面談なら具体的な助言もできますが、一般的に言えることはあまりありません。良いアドバイスを望むなら、信頼できる人に相談するのがいいでしょう。それこそ、情熱があるなら協力してくる人は多いはずです。
当たり前のこととして、良い準備ができた人が勝利に近づきます。ここでは、その準備の準備として「良い」の基準を確認していきたいと思います。評価基準や採点方式はコンテストごとに異なりますが、だいたいのマジックコンテストでは不思議さ、技術、構成、プレゼンテーション、ショーマンシップ、エンタメ性、芸術性あたりが評価対象になります。エンタメ性のみ評価するというコンテストもあるかもしれません。ルールに応じた最適化をしてください。ここからは、マジックコンテストの最高峰であるFISMの観点を見ていきます。
審査の観点
専門技術 Technical Skill/Handling
人生はお金ではありませんが、人生にはお金が要ります。そのパラドックスがマジックと技術にもあります。マジックにとって技術は最終的には重要ではないかもしれませんが、技術がないと始まりません。そして、技術から自由であるためにはかなりの技術が必要です。
技術で重要なのは超絶度ではなく熟達度です。自然さ、スムーズさ、確実性、安定性、ステルス性、自在性などを見ます。技術の選択が適切かというメタ視点もあります。
超絶技巧でアピールする必要はありません。スゴ技をキメて高得点というのもいまどきないでしょう。無駄に難しいことをするのは不適切な選択とも言えます。ただし、スキルデモンストレーションがテーマのアクトなら話は変わってきます。
基本的には安定運用できる範囲の技術を使うべきです。その範囲を確保するために技術を高める必要があります。超絶技の練習も技術の幅を広げるのに役立ちます。
スライト以外にも、ミスディレクションやサイコロジカルテクニック、あるいはギミックやテクノロジーも技術に含まれます。基本的な考え方はスライトと変わりませんが、ギミックの場合には、とりわけ見せない技術、感じさせない技術が求められます。ギミックが見えたり匂ったりするとスライト以上に印象に影を落とします。
ギミックが感知される(ギミッキーである)ことと、ギミックだと推測されることは違います。カッパーフィールドのフライングは装置であろうことが推測されるわけですが、ギミッキーではありません。それに対し、ポールに沿って直線的に上昇する浮揚はギミッキーです。まるで違う印象になります。印象上、前者は魔法であり、後者は非魔法です。
ショーマンシップ/プレゼンテーション Showmanship/Presentation
ショーマンシップはいわば演者力です。マジックが弱くてもショーマンシップで魅せられたり、強いマジックがショーマンシップで台無しになったりします。乗算的な働きがあるので、その影響力を考えると、必ず高めておきたい項目です。良い演者を見てショーマンシップを学んでください。マジック以外の演者も参考になります。
ショーマンシップは磨いておくべきものですが、ショーに臨む際の意識も重要です。ショーマンシップへの集中は緊張にも効きます。そもそも緊張は、出力を高めるための生理反応です。エンジン全開、走らないと震えます。実際、意識を内に向けると手が震えます。外に向ける必要があります。ショーマンシップのギアを上げましょう。アドレナリンがパワーに変わります。
プレゼンテーションは、マジックをショーにするための有形無形の手段すべてです。ペルソナ、衣装、セリフ、道具立て、音響、照明、客あしらい等々。それらがマジックや演者に合っているのか、すべてで調和や整合性が取れているのか、そしてそれは結局おもしろいのかというのが問われます。
プレゼンテーションに関しては、それだけで本が書けます。実際にいくつもの本が出版されているので、それらを読むと良いでしょう。
エンタメ性 Entertainment value
エンターテインメントとしてのおもしろさです。どれぐらい観客を楽しませられるものなのか。
ここでは実際の客ウケも見ます。当然それはエンタメ性の指標になります。ただ、内輪ウケはあまり評価されせん。コンテストの観客は特殊であり、特有のツボがあります。ツボを突けばリアクションが得られますが、それは足の裏をこそばすようなもので、良いエンタメではありません。ウケには量だけではなく質もあるということです。下品、卑猥、低俗、悪趣味なものはウケても低評価になる恐れがあります。
ウケはアクトが置かれるコンテクストにも依存します。イベントを通じての波もありますし、直前の演目にもかなり左右されます。場外戦が影響するかもしれません。審査はコンテクストでブレるべきではありませんが、人間が見る以上、排除しきれるものではないでしょう。実際のところ、なんであれ、ウケるとかなり有利です。
芸術性/構成 Artistic Impression/Routining
マジックは芸術かという議論を好むマジシャンは多いのですが、それは、マジックをどう考えるかというよりは、芸術をどう考えるかの問題になります。マジックは、芸術になりうるとも思いますが、その前にイリュージョンが成立していなければならず、その後にエンターテインメントでなければなりません。その意味で、マジックは、少なくともマジックコンテストの文脈では、純粋芸術にはならないでしょう。
芸術にはいろんな形がありますが、根本的には真善美を追求するものだと思います。当然、マジックにも真善美の追求があり、それが極まったときにそれは芸術的なものになります。
マジックが芸術性を帯びるとき、それは普遍的で超越的な価値を持つという点ですばらしく、また、それがもたらす快感情は観賞感を大きく高めます。当然、それは高く評価されるべきものでしょう。
芸術性には構成によるものがあります。なので、構成と芸術性がひとつの観点にまとめられているわけです。とはいえ、個人的には別の観点とする方がわかりやすいと思っています。それらは重ならないところも多いからです。もっとも、後ほど見ますが、FISMの採点方式においてその辺の仕分け方はあまり重要ではありません。
芸術的な構成は、全体に全体像があり、部分に全体の精神があります。要素自体、そして要素間のつながりに必然性があります。テーマでまとまっていると言ってもいいでしょう。トートロジーになりますが、そこに芸術性があるとき、芸術的だとなります。基本的には感性に訴えかけるものです。観念的な芸術性は、見る側の芸術観にもよりますが、評価されにくいと思います。マジックの芸術的側面は、見出すものというよりは感受されるものになります。
パフォーミングの芸術性もあります。動きに全体性があり、完全性があり、秩序があり、調和があり、リズムがあり、洗練されており、道具の扱いが自然であり、軽やかであり、自由であり等々。非常にざっくり言うと、所作が美しいということです。結局、美的感覚で判断するしかありません。
独自性 Originality
独自で考えたものが独自性のあるものとは限りません。他にはない質を持つものが独自性のあるものです。他にはないものを考えるためには、周りを知らなければなりません。他に似ないようにあえて他を見ないという人もいますが、それはもともと特殊な人で、幸運に恵まれないとうまくいきません。当然ながら人は普通、特殊ではありません。人間が考えることはだいたい同じです。Think differentというアップルの広告に突き動かされた人が皆マックを買いました。
独自性は本来、目的ではなく進化の側面です。キリンの首が長いのは、高いところのエサがとれるからです。ゾウの鼻が長い理由は知りませんが、少なくとも斬新なスタイルを目指したものではないでしょう。生物の独自性は、図らずも、生態系における優位性に導かれています。
人間活動はもっと意図的なものかもしれませんが、そうであっても、むしろそうであるのならなおさら、独自性の焦点は形ではなく機能に当てられるべきでしょう。それは何を達成するものなのか。新しい何かをつかむとき、必然的に独自の形になるのです。
表面的な奇抜さを追う必要はありません。利点を伴わないエキセントリックはほとんど評価に値しません。新しいだけのパターンは無限に生成できます。ピアノの鍵盤をデタラメに叩けば新しい曲が(曲と呼んでいいのかは知りませんが)できますが、そこに何の意味があるのでしょうか。
表面的にならないようにすべきです。ただ、表面的にでも何かに似ていると、印象が弱くなるので、他と類似する形態は避けたほうがいいでしょう。それぐらいの制限は、創造を阻害するものではなく、むしろ促進するものになるはずです。
魔法感 Magic Atmosphere
魔法感はマジックの必須条件になる項目です。マジックコンテストですからマジックでなければなりません。日本においては、しばしばこの項目が「不思議さ」と置換されます。不思議を目的化した芸が奇術=カタカナのマジックなので、マジックの要件が不思議さになるのはそれこそ不思議ではありません。一方で、英語のmagicは、本来の意味が魔法なので、magicと呼ぶためには魔法を感じさせなければなりません。魔法は不思議、ゆえに不思議を見せようとなり、そこでめでたくマジックと合流します。しかし、魔法が不思議だとしても、不思議が魔法とは限りません。スマホや電子レンジも不思議ですが魔法ではありません。メタファーとしては魔法と言えるかもしれませんが、我々のmagicはメタファー以上のフィクションです。したがって、magicにはその根底に魔法味への志向性があります。それがMagic Atmosphereの本質だと思います。
マジックとmagicのニュアンスの違いは、日本のマジシャンと海外のマジシャンの態度の違いにも表れます。日本のマジシャンは、魔法のイメージから自由であり、それゆえのおもしろい発想があります。海外のマジシャンは、「魔法ならどうか」という意識が強く、それが表現の質になっています。
そういうわけで、国際コンテストでは魔法をより意識した方がいいかもしれません。実際には、日本においても魔法的なほうが好まれます。「ひっかかった」「わからなかった」と「魔法だった」でどちらが印象的でしょうか。
もっとも、魔法的であるためにも不思議は必要です。そして、競技においては不思議なほど良いです。一般的に見て不思議というレベルは、競技ではヌルいものになります。マジックの要件としてはそれで十分ですが、加点要素にはなりません。可能なら審査員をひっかけましょう。そのほうが評価が高くなる傾向があります。
不思議には「わからない」と「ありえない」がありますが、これらは違います。「わからない」はメソッドの見当がつかない状態であり、「ありえない」はメソッドの存在不能を言うものです。もちろん「ありえない」の方が上です。合理的手法が存在しないときに魔法しかないということになります。非魔法の否定による魔法の肯定です。この否定の否定が、魔法性へのアプローチのひとつです。
その二重否定を単純肯定にできないでしょうか。それがもうひとつのアプローチです。
我々はカテゴリを直観的に判定するシステムを持っています。プロトタイプ理論です。たとえば、パネルを見せて鳥か否かを答えさせるテストをすると、スズメやカラスより、ダチョウやペンギンの方が反応が遅くなります。前者は鳥のプロトタイプ(原型)に近い形態なので直観でわかりますが、後者はプロトタイプでは判定できず、知識で対応することになるので判断に時間がかかります。魔法にもプロトタイプがあります。あるいは、おそらくアーキタイプ(元型)のようなものもあります。マジックをそこに近づけると「魔法である」という印象になるわけです。Magic Atmosphere の美しい、ある意味では本来的な達成になります。
映画やアニメの魔法が、なぜ魔法として瞬時に受容されるのか。ひとつには、魔法のアーキタイプやプロトタイプを利用しているからでしょう。そして、それらの魔法の映像表現が、再帰的に魔法のプロトタイプを作ります。
魔法のプロトタイプはマジシャンにもっと意識されて然るべきものでしょう。マジシャンは魔法の虚構を見せる役者です。
採点方式
採点方式には大きく2つあります。項目ごとに採点して項目点の合計を最終点とする方式と、いくつかの観点から全体を総合的に評価して採点する方式です。これらを項目点式と全体論式と呼ぶことにします。FISMは後者です。
私自身はもともと項目点派でしたが、いまは全体論派です。マジックの良さが要素の単純な足し算になるとは思えません。すでに見たように、乗算的な要素もあれば、要素間のシナジーやアナジーもありますし、要素が統合される際の創発もあります。また、要素のウェイトは、マニピュレーションとメンタリズムで、もっというと各アクトごとにも違ってくるでしょう。
認知的な限界もあります。我々が経験するのは統合後の全体です。それが何で構成されているのかはあまりわかりません。おいしいカレーの隠し味を当てるテレビ企画で、どの専門家も正答できませんでした(答えは砂糖でした)。何が貢献しているのかわからないまま、おいしいことだけわかるのです。だから隠し味になります。
印象の理由を求められたとき、我々はしばしば無意識に理由をでっちあげることが知られています。項目点式でもでっちあげが起こります。わかりやすい例は、さほど不思議ではない名演に対する不思議点のかさ上げです。仕方がないところもあります。そこを低くすると総合点が低くなってしまいます。秀でたものが秀でた点にならないのは、ルール上は正しいのかもしれませんが、評価として正しくない気がします。その不協和を解消するため、そのアクトは不思議だったことになります。技術点でもそれは起こりますが、それに関しては、優れた芸であるなら技術があるという見方も可能です。しかし、なんにせよ、アクトの印象を項目点に振り分けるなら、最初から全体論でいいわけです。
項目点式のメリットは説得力でしょう。客観性や再現性があるように思えます。なので私も項目点派でした。全体論には説得力がありません。80点の根拠が「総合的に判断して」では納得感がありません。ただの主観ではないかと。実際、全体論式は多分に主観です。客観性や再現性を放棄しているようにすら感じられます。それでいいのでしょうか。どうやらよさそうだというのが私の見解です。
私の経験上、全体論式のほうが不思議と再現性が高い、つまり、採点のブレが少なくなっています。というか、項目点式が思いのほかブレます。それだけ項目点を付けるのは難しいということでしょう。カレーを食べたとき、おいしさ点はすぐ付けられても、スパイス点とか具材点とかライス点とかを聞かれると困惑するのではないでしょうか。部分の評価は考え方によっても変わります。でもおいしさは考え方ではありません。そして、考え方より感じ方の方が実はそろいやすいのです。
「客観的に」と言うとき、多くの場合、それは間主観的なものです。同意が成立する主観ということです。例えば美人というのは間主観的なもので、主観のコンセンサスで決まります。良いマジックも間主観的なものです。そもそもマジックは客観的には存在しません。マジックは観客の脳内で起こるものと言われる通り、主観的経験を作るのがマジックです。そして、観客が一様に錯覚し、良いイリュージョンを見るのが良いマジックです。そう考えると、一定レベル以上のマジックにおいて、主観的評価がそろうのは不思議ではないのかもしれません。
実は再現性が高いというのがわかって私は全体論派になりました。あとは速く採点できるというメリットもあります。悩まなければ数秒でできます。そして、アクトの美点を尊重した評価ができるのも良いところでしょう。観客を魅了する何かがあるとき、それがどの項目に属するものであれ、そこには大きな価値があるのです。
国内大会は丸いものが勝ち、国際大会は尖ったものが勝つとも言われることがありますが、それは採点方式の違いによる場合もあります。もっとも、ほとんどの場合はレベル差です。国内大会であればすごくうまければ勝てます。でも、国際大会はすごくうまい人が出るので、それだけでは勝てません。プラスアルファが求められます。これは、丸の上のエッジであり、ウィークポイントに寛容というわけではありません。国際大会で勝つアクトは国内大会でも採点方式によらず勝つ(圧勝)でしょう。
ところで、全体論式の観点は何のためにあるのでしょうか。観点のスコアを飛び越えて総合点が付きます。観点が定められていなくても点数が変わらなそうです。実際にそうかもしれません。観点は観る点です。フレームの設定と言ってもいいでしょう。フレーミングで印象が変わりうるのでそこの統一です。とはいえ、特別な見方が要求されるわけではなく、だいたいは順当なフレームが確認されるだけなので、それで見方が大きく変わることはありません。また、観点の間にはかなりの重複や冗長性がある(多くはエンタメ性で回収できる)ので、観点のリストが多少違っても大枠はほとんど変わりません。なので、よほど特殊な観点が設定されない限り、その有無や違いによる影響はあまりないでしょう。ただ、観点がいかに順当なものだとしても、順当であることを明確にしておくのは重要です。
観点の確認は、排除されるべき価値基準の確認でもあります。例えば、プロフィールやルッキズムが審査に影響することはルール上ないといったことがわかります。実際、定められてない基準が持ち込まれることがあってはなりません。審査員にはその徹底が求められます。そういう管理ができる人が審査員をすべきです。
では、審査に要求される資質を見ていきましょう。
審査員の適性
フェアさ
コンテストにフェアさは欠かせません。フェアではないコンテストは出来レースです。ルールをあからさまに無視する意図的な優遇や冷遇はほとんどありませんが、無意識の先入観や偏見が入ることは割とあるでしょう。先入観や偏見を全く持たない人もいませんが、それが少ないこと、そして、それが正しくないとわかっていることが重要です。
専門知識
専門的な卓越性を評価しなければならないので、専門知識は当然必要になります。
眼力
解像度と判定精度です。解像度がないと細部が見えません。神は細部に宿ります。それが見える視力が求められます。そして、細かく見えたとして、それらの良し悪しを見極める目も求められます。正しさが感覚的にわかるのかということです。
感性
エンタメ性や芸術性を評価するには、それらに対する適切な感受性がなければなりません。
パラレル視
マジックには表と裏があります。一般客が見るのは表ですが、マジシャンには裏も見えてきます。それはかまわないのですが、それで表が見えなくなってはなりません。マジックを評価するには表と裏を同時に見る必要があります。難しい場合、表に集中できたほうがいいです。
教養
すべてのマジックは何かしらの知識を前提にしています。不思議は自然に対する常識が前提になっていますし、テーマによる意味付けや趣向は社会常識が前提になっています。それらがないとマジックはビックリ箱にしかなりません。ある方面に暗いと、そこにかかるテーマが十分理解できません。審査員には幅広い知識が期待されます。高度な知識ではなく、常識的な知識でいいのですが、あらゆる常識をカバーするのはなかなか大変(まあ無理よね)です。
ひっかかりにくさ
ディセプティブさ30でノックアウトされたら、40と80の違いがわかりません。そこを測るにはかなりの耐性が必要です。しかしながら、ひっかからなかったもののグラデーションを見るのも実際には難しく、そこが白黒判定になるなら標準的なひっかかりやすさのほうがいいかもしれません。
一般の感覚
審査員には一般以上の感覚が求められるわけですが、一般的にはどう感じられるのかもわかっていなければなりません。その縦軸とは別に、横軸の一般もあります。個人の趣味を押し付けないということです。辛いのが大好きだからと言って、激辛カレーを優遇してはなりません。審査は主観になるとは言いましたが、これは好き嫌いで採点するという意味ではありません。我(が)と交わる前の質を見極めなければなりません。間主観的主観ということです。
国際感覚
間主観はインターサブジェクティブで、ネイションレベルでのそれがインターナショナルになります。したがって国際感覚は海外風の感覚ではなく、国境なき感覚です。当然、国際大会とリンクする大会ではそれが重視されます。もっとも、場所に依存しない普遍性はそれ自体が価値の高いものです。
以上の資質を兼ね備えている人が審査員として理想ですが、これは理想論です。そんな人はいません。いるなら審査員はその人だけでいいでしょう。それができないので複数人で審査します。三人寄れば文殊の知恵で、数でスコアは適正化されます。ジャッジミーティングでエラーは修正されます。もちろん、それでも間違いは起こります。採点競技の宿命でしょう。
最後に
書いているうちにだいぶ長くなってしまいました。これでもだいぶ削りました。
必勝法はないと言いましたが、必負法のようなものはあります。よくある悪い例をいくつか書いていましたが、否定的なトーンが強くなりすぎるので今回はカットしました。
なお、これはどこかの公式見解ではなく、私の現時点での個人的見解です。偏った見方もあるかと思います。同意していただく必要はありません。これによって別の見解が明確になるのなら、それは喜ばしいことです。とりあえずコンテストにかかわる方、かかわろうとする方にとって何かしらの参考になれば幸いです。
ポン太 the スミス