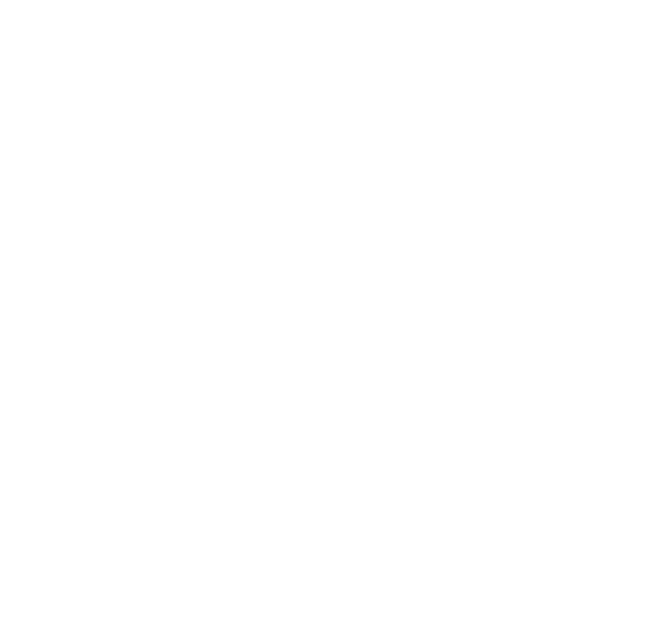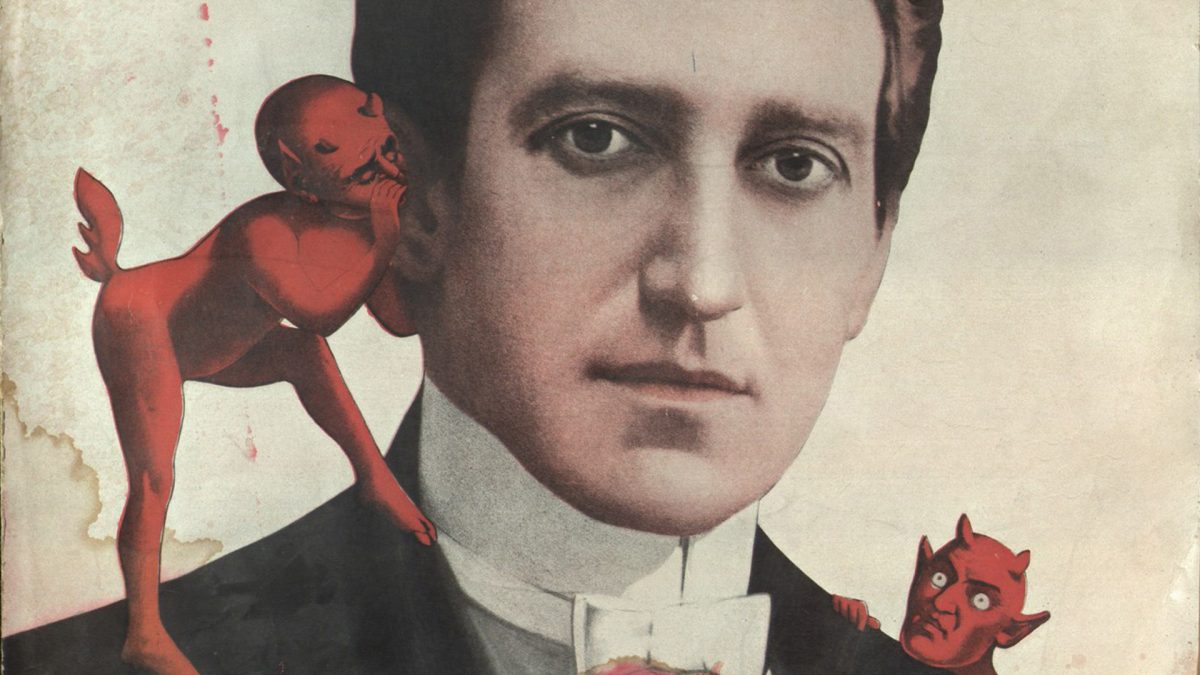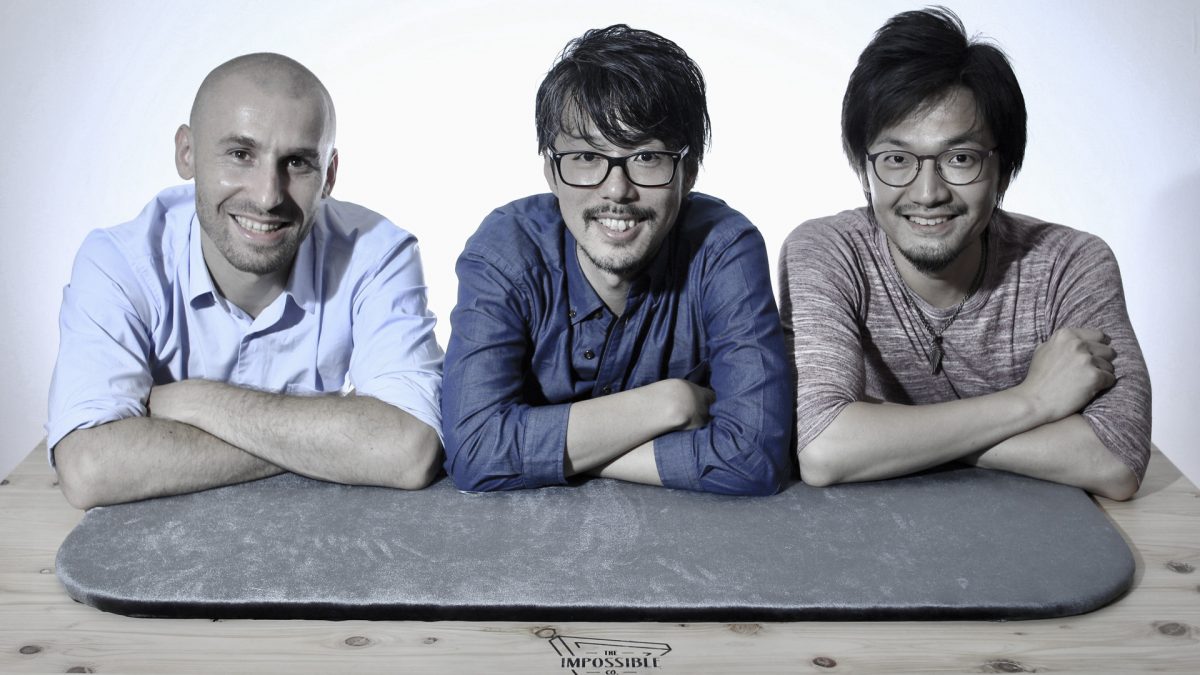ミスディレクションとはご存知の通り観客の注意を逸らす技術です。
マジシャンのあいだでミスディレクションの重要性は広く認識されていますが、見落とされがちなのはミスディレクションにおける程度の重要性です。
何かに注目しているときに他のことが見えなくなることがあります。この見落としは非注意性盲目とも呼ばれ、バスケットボールのパスを数えていてゴリラの乱入に気づかなくなる「見えないゴリラの実験」が有名です。非注意性盲目を引き起こすのが、強いミスディレクションになります。
注意力のリソースは有限なので、使われすぎると他に割く注意力がなくなり、網膜に写っているのにもかかわらず処理がなされず事実上見えなくなる、という原理です。
奪われる注意がそれほど強くない場合は、注意力が残るので盲目は起こりません。それでも注意力が削がれた分、情報処理レベルは落ちます。運転中に通話すると、盲目にはならなくても判断が鈍るために事故が増えます。このように情報処理のレベルを低下させるために使うのが弱いミスディレクションです。ディバイデッドアテンションという言い方がこの場合わかりやすいと私は思っています。
2つに分けて説明しましたが、実際には2種類あるというよりも、注意をどれだけ奪うかという量的な話であり、あるレベルで盲目が生じるイメージです(対象物のサイズや位置によっても盲目ラインは変わります)。
ミスディレクションは、程度を正しく選ぶことが重要です。盲目性が必要とされる場面で、見えてしまうのはもちろんアウトですし、低レベル処理が求められる場面で見えないのもまた良くありません。
盲目性が目的だからといってミスディレクションが強ければ良いわけでもありません。何かに気づかれないためにミスディレクションを使うわけですが、ミスディレクション自体にも気づかれてはなりません。「注意は逸らされていない」と観客に思ってもらえるよう、ミスディレクションはなるべくサトルに行うべきでしょう。
次のブログでまたミスディレクションに関連するトピックを取り上げます。
ポン太 the スミス