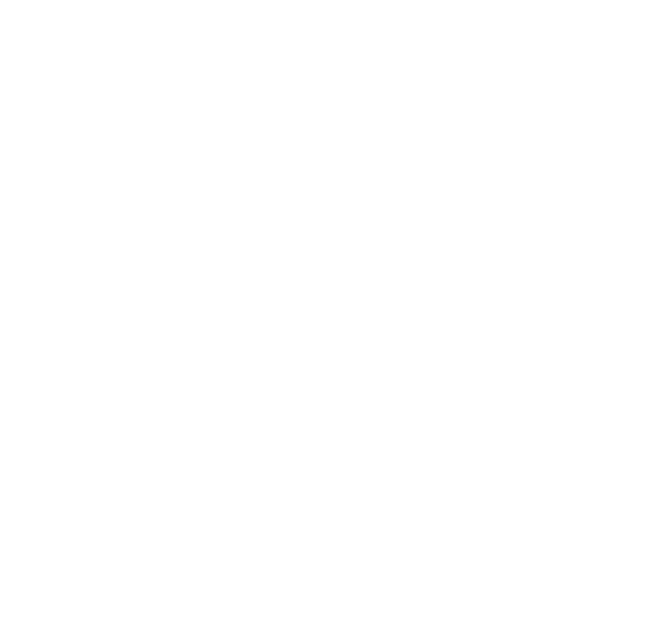間(ま)が大事だというのは、マジックに限らず、あらゆる分野のプレゼンテーションで言われることです。プレゼンの上手と下手を分けるのが間と言っても過言ではないでしょう。マジックの場合、間の取り方で秘密に意識が向いたり向かなかったりするので、一層気を付ける必要があります。
間は、事前の間と事後の間に分けられます。
事前の間というのは要するに現象前の間です。マイク・スキナーがその間を強調していたとジョン・カーニーから聞きました。awkward pause とスキナーは表現していたそうです。会話中などでの気まずい沈黙を指す言葉です。何もない空白の時間が発生すると、人は入力を欲します。そのタイミングで情報を出せば食いついてもらえます。刺激に対する感度が上がるわけです。焦らしとも言えるでしょう。逆に間を十分に取らず、空白が整わない段階で刺激を与えても、鈍い反応にしかなりません。ひどいときには「ごめん、よく見ていなかった、もう1回やって」となりますが、そういうケースも案外少なくありません。何もしないのが気まずいので、すぐにやってしまうのですが、その気まずさこそが大事にすべきモーメントだということです。
事後の間は、appreciationとジョン・カーニーが言っていました。認識を深める時間です。情報の処理には深浅があります。間を置くと処理は深まり、間をおかないと処理は浅くなります。例えば「彼女は指輪を海に投げた」という文章を見たとき、まず字義どおりの情景を理解し、その後に、その背景の解釈へと処理が進みます。文章をここで切らずに、「彼女は指輪を海に投げたが、飛んでいたカモメがそれを食べ……」と続けると、処理が情景の理解から背景の解釈へは進まずに次の情報の処理に移ります。マジックではそのように浅く処理させたほうが好都合な場合もあります。例えば、フォールストランスファーは消失後に反対の手が疑われるという問題がありますが、消したボールをすぐにカップから出現させれば、消えた原因に観客の意識が及びません。ポール・ダニエルズのチョップカップルーティンはそのような連続で構成されています。一方、ガイ・ホリングワースはボールの消失を深く印象付けるために、完全消失にしてゆっくり間を取っていました。どちらが良いかは好みなのですが、重要なのはそれに合った間を選ぶ必要があるということです。間を逆にするとどちらも機能しません。
間の長さ関しては、テンポ全体がそうなのですが、遅いと感じるぐらいがたぶんちょうどです。英語ネイティブと英語学習者のあいだで英語の処理速度に差があることは誰もが理解していますが、マジシャンと非マジシャンのあいだでマジック(現象)の処理速度に同様の格差があることを我々は忘れがちです。特に自分がやりこんでいるマジックの処理は高速化されています。自分が見て心地よい間やテンポでやってしまうと、現象の処理が追いつかないことになってしまいます。なにをやっているのか分からないと観客に思わせてしまうのもよくある失敗です。
間の最適化だけで、印象は一変します。ご研究ください。