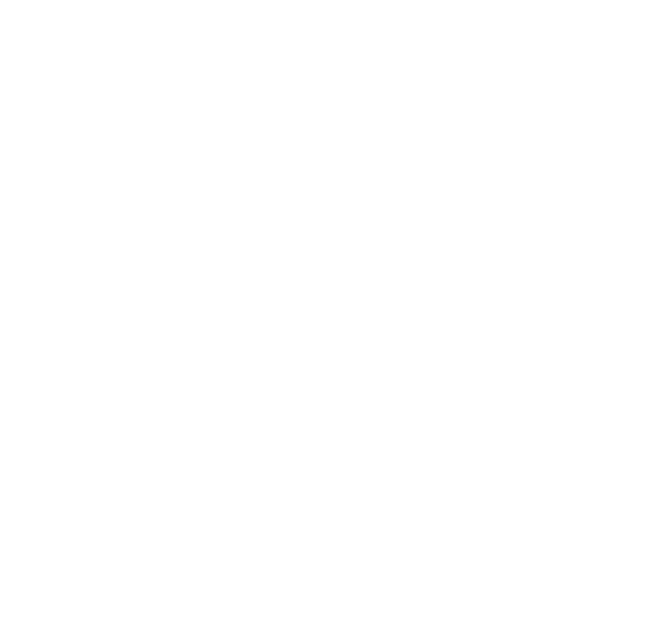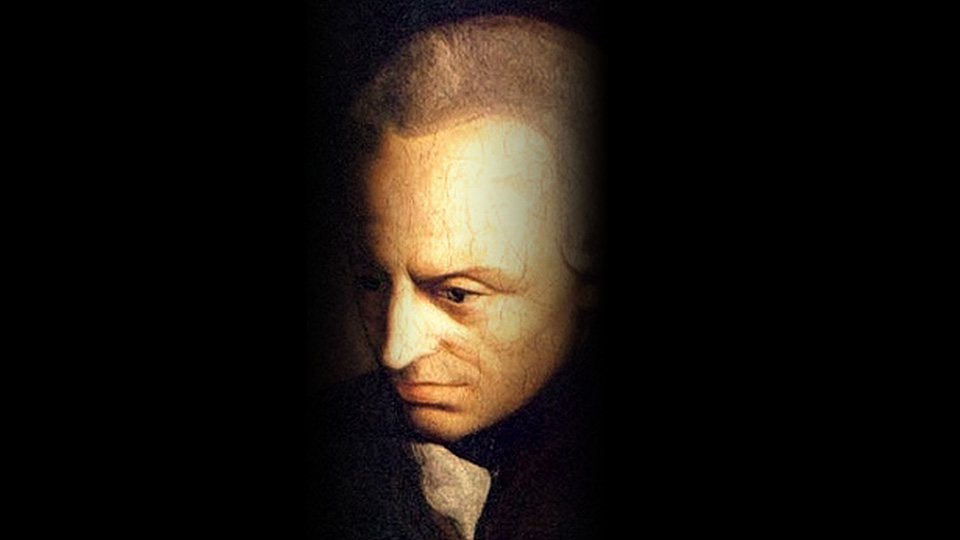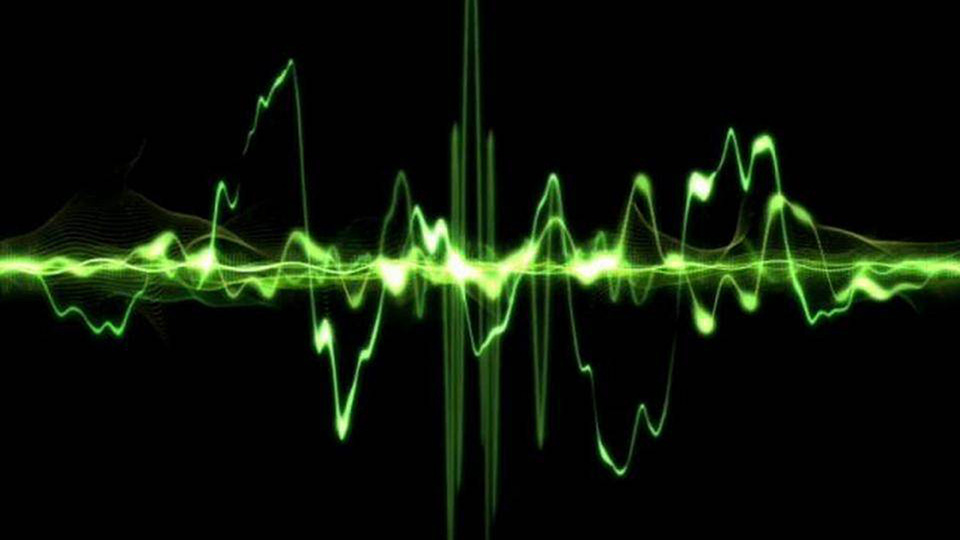「概念なき直観は盲目である」 ―― エマヌエル・カント
日本ではどうもマジックの理論が軽視されているように思います。それは、私が「理論の必要性」というブログを書く必要性を感じるほどです。
セオリーが万能だと言うつもりはありません。実はむしろあまり頼りにならないものです。トミー・ワンダーも言っていますが、選択が正しいかどうかの判断に、セオリーを使うのはそれこそ正しい選択ではなく、そこは感性で見極めなければなりません。理論上おいしい料理が実際においしいかどうかは、食べて確認する必要があるということです。料理人に味覚のセンスは不可欠です。
センスは、五感に代表されるように感じる能力です。センスがないと結局は間違えます。He love you.と私が平気で間違えるのは、三単現のsのルールを知らないからではなく、そのエラーに違和感がないからです。He you love.とまでは間違えないのは、SVOの知識があるからではなく、その語順に違和感を覚えるからです。それが語学センスです。ネイティブスピーカーは、文法の知識がなくても、感覚を持っているので文法を間違えずに話せます。必要なのは知識ではなくセンスです。
マジックもセンスがないとうまくいきません。まずセンスを養う必要があります。センスを養うにはとにかく良い物を見ることが重要です。良い物を選ぶのもセンスなので、鶏と卵になるのですが……。良い物に触れるうちに、なんとなく「わかる」ようになります。それがセンスです。
次に養ったセンスを磨きます。当然のこととして、明確にわかる範囲の外になんとなくわかる領域があります。感覚的にはわかるけど論理的には説明できないことはたくさんあるはずです。そこを理論によって言語化・論理化して理解を明確にします。で、ここが重要なところなのですが、明確にわかる範囲が広がると、感覚的にわかる領域が広がります。アキレスと亀のように、論理が感覚に追いついたとき感覚はさらに先に行っているのです。
論理か感覚か? などと言われることがありますが、その両輪がそろって前に転がります。センスだけでは限界があり、そこから先に行くためには論理的な分析が不可欠です。そこで理論が役立ちます。
というわけで今後もこのブログでは理論の話をしていくつもりです。
ポン太 the スミス